こんにちは、makkyです。
今回は、僕が実際にスマートホームを導入して「これは困った!」と感じたこと、そしてその対策についてまとめます。
これからスマートホームを始める方に向けて、リアルな体験談をお届けします!
憧れのスマートホーム、でも意外と落とし穴も?
「アレクサ、電気つけて」
「アレクサ、エアコン消して」
こんな未来的な生活に憧れて、EchoデバイスやSwitchBot製品をそろえた僕ですが、導入当初は想像していたほど完璧ではありませんでした。
実際に使い始めて分かった、「思わぬ落とし穴」について紹介します。
僕が実際に困ったこと
1. 赤外線が届かない問題(リビング→書斎)
SwitchBotハブミニは赤外線で家電を操作しますが、壁を挟むと信号が弱くなり、書斎のシーリングライトがうまく反応しないことがありました。
最初は「設定ミスかな?」と思っていましたが、赤外線の見通しが悪いと届かないという基本的な問題でした。
2. テレビのスマートプラグONで自動起動しない問題
リビングのテレビをAmazonベーシックスマートプラグに接続して、「電源ONでテレビも起動する」と期待していましたが…。
実際はプラグを入れてもテレビがスタンバイ状態に戻るだけで、画面は表示されませんでした。
(テレビの機種によっては自動でONにならないことがあるようです)
3. Echoが複数あると反応がズレる/重複する
リビングと寝室にそれぞれEchoを置いていると、声をかけたときに両方のEchoが反応することがありました。
タイミングによっては「違う部屋のライトがつく」という事故も発生…。
4. スマートタップでPCを再起動してしまう恐れ
書斎のパソコン周辺は、merossのスマートタップにまとめて接続していますが、間違ってPC本体までOFFにしてしまうと作業中のデータが飛ぶリスクがありました。
一括制御は便利ですが、重要な機器には注意が必要だと痛感しました。
5. Wi-Fiやクラウド依存のリスク
スマートホーム機器はほぼすべてインターネット依存です。
Wi-Fiが不安定なときは、音声操作ができなかったり、遅延したりすることもありました。
通信環境が安定していることがスマートホームには必須です。
実際どうやって対処したか
● ハブミニの設置場所を工夫
リビングと書斎の間にハブミニを置くことで、両方の赤外線操作が安定するようにしました。
見通しが良くなるだけで、かなり操作成功率が上がりました。
● テレビの電源設定を変更
テレビ本体の設定で「電源ON時に入力切替を自動でON」にするモードがあり、それを有効にすることである程度改善しました。
もしできない機種なら、スマートプラグではなく赤外線リモコン操作の方が確実です。
● 各Echoに「デフォルトデバイス」を設定
Alexaアプリの設定から、それぞれのEchoデバイスに「どの部屋の家電を担当するか」を指定しました。
これで、同時に複数台反応しても誤動作を防げます。
● スマートタップには「待機電力用」機器だけ接続
PC本体は通常の電源タップに接続して、スマートタップにはモニターやライトなど電源を切っても問題ない機器だけを接続するようにしました。
● 通信トラブル時は「物理スイッチ」も併用
一応、手動リモコンも近くに置いておくようにしています。
完全スマート化だけに頼ると、もしものときに困るので…。
まとめ|トラブルもあったけど、それ以上に快適だった
スマートホームは、導入直後はちょっとしたトラブルがつきものですが、対策をしていけば本当に生活が便利になります。
僕も今では、朝の電気・エアコンON、夜の一括OFFが手放せない習慣になりました。
これから導入する方は、ぜひ「困ったときの工夫」も考えながら、少しずつ快適なスマートライフを作っていってください!
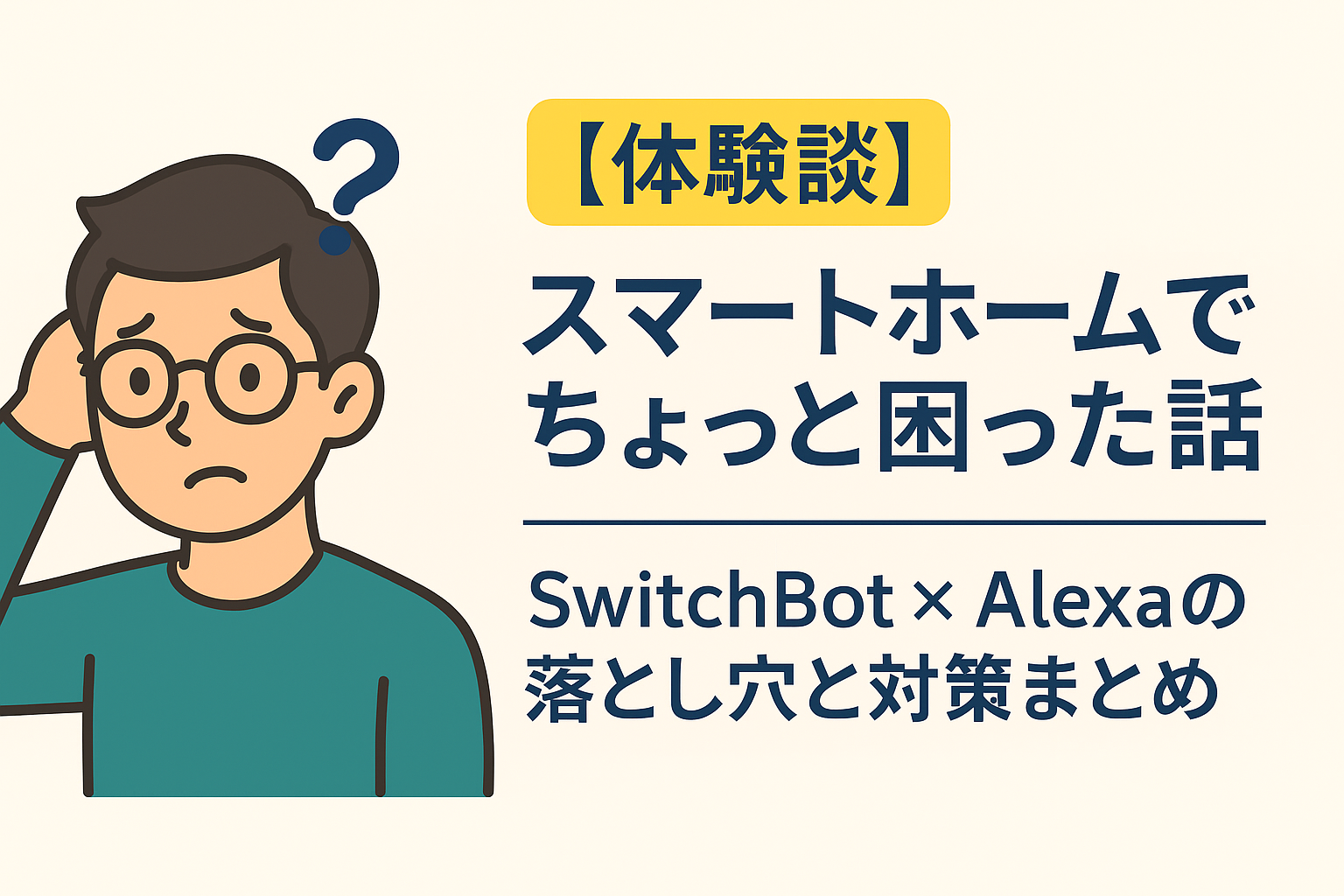

コメント